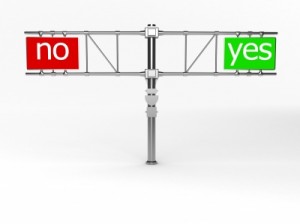
だいぶ昔のことですが、会社の研修でとても面白いものがありました。
まず研修生は8つほどのチームに分かれます。それぞれのチームは「アメリカ」「イギリス」「日本」「中国」「ブラジル」「フィリピン」などの名前が付けられています。それぞれのチームにはA4の普通紙や定規やコンパス、はさみやカッターナイフが配られています。これらの紙と道具を使って指定された三角や四角、丸などの「商品」を作ると、それを教官が運営する「銀行」が買い取ってくれる。ルールはカンタン、いかに多くの「商品」を作りそれを売って金を儲けるか。もちろん最も多く稼いだ国が優勝です。
このゲームが面白いのは、ゲーム開始の段階で各国が持っている「資源」=紙と「加工技術」=道具の量や割合が現実世界のそれとほぼ同じであること。例えば、日本はほとんど紙を持っていない代わりに、定規やはさみはふんだんに持っています。一方中国やブラジルはカッターナイフだけしか持っていなかったりしますが、その代わりに紙は大量に保有しています。当然国家間の交渉、つまり「貿易」は可能で、そこにはルールがありません。物々交換でもいいし、金銭のやり取り、さらに売掛買掛でもいい。とにかくゲーム終了の段階で金を最も儲けたチームが勝ちとなるわけです。
このゲーム、やっぱり勝ちやすいチームと勝ちにくいチームがあるそうです。日本や中国は勝ちやすい。一方、イギリスやフィリピンは勝ちにくいそうです。
なぜか。
それは戦略構築がカンタンだから。例えば日本は資源はほとんどなく、加工技術しかありません。つまり資源を輸入して製品を輸出するしかないわけです。中国も同様。資源しかないので、豊富な資源を活用するしか方法がありません。一方で、イギリスやフィリピンは、加工技術も資源もほぼ同程度持っています。このため、資源ベースで戦略構築するか、加工技術ベースで戦略構築するか、多くのチームが決めかね、判断が遅れ、そして破れていくわけです。明確に選択と集中の判断ができないために、例えば「資源立国を目指すため自分の持っている加工技術を全て売り払う」といった思い切った交渉ができない。結果乏しい資源と乏しい技術でそこそこの金を稼いで、下位に甘んじる。
「戦略とは捨てることである」とはよく言ったものですが、まさにこの「選択と集中」の決定、取捨選択による資源配分の最適化こそが戦略であり、その判断をいち早く下した者が勝つわけです。
まれに「イギリス」や「フィリピン」が勝つこともあるそうですが、その場合は必ずと言っていいほど戦略決定が早いそうです。当然それ以外にも交渉上手など他の要素もあると思いますが。
これは人生においても同様なのではないかと思います。
例えば趣味と仕事。こんなこと言ったら多くの先人たちや友人たちに笑われてしまいますが、学生時代は趣味であるDJを仕事にしたいと本気で思っていた時期もありました。その一方で、これまで中学高校大学生活で培ってきた普通の人生も捨てがたい。迷った僕は結局普通に就職しました。当然ながらDJに割ける時間は減ります。昔は平日のパーティも気兼ねなく行けたのに、会社に入ってからはさすがに火曜午前3:00からのDJの仕事は受けられない。結果としてDJはただの趣味になっていく。
一方で仕事はどうか。こっちはこっちでダメ。DJへの未練が残っているがゆえに、ちょっとでも仕事がつまらなかったりすると「この仕事は本格的にDJを始めるまでのツナギなのだ」なんて思ったりする。そのため、仕事に身が入らない。成長できないし結果が出ない。
僕が持っていた「資源」や「加工技術」が多かったか少なかったかは定かではありませんが、僕の感覚ではそれらは同程度でした。結果としてイギリスやフィリピンのように判断が遅れ、片方にどっぷり浸かるという思い切った判断ができず、下位に甘んじることになるわけです。
この研修は、そのことを僕に気づかせてくれたわけです。
このような判断は人生の至る所で求められます。有限である時間や脳ミソをどう配分していくか。「営業」か「技術」か、「自動車業界かIT業界か」、「AプロジェクトかBプロジェクトか」、そして「ワーク」か「ライフ」か。時には二兎を追わなければならないシチュエーションも少なくないでしょうが、自分の腹の底では常に「選択と集中」の心構えを持っておくのが肝心なのでは!と、フィリピンチームに所属して予想通りの惨敗に打ちひしがれながら当時の僕は痛感した次第です。
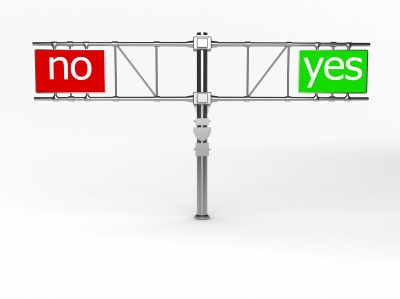
コメントを残す