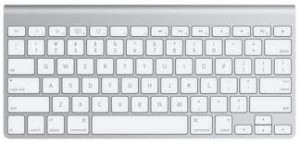
ある時期からパソコンの入力装置にちょっぴりこだわるようになりました。
自宅のパソコンはMacなので秀逸なApple製品で全然問題ないのですが、会社のパソコンは付属のマウス&キーボードがなんか使いづらいなーと。
使いづらいというより、より一層快適にしたい!と思うように。
最初に買ったのはHappy Hacking Keyboard Lite。
プログラマーなどに人気のキーボードだそうですが、個人的には数字キーを排除したストイックな感じに惹かれました。
が、あまりの突飛なキー配列に結局最後まで慣れきれず。
で、ふと思ったのが「Apple Keyboard」でいいじゃんというアイデア。
これなら自宅とも操作感が一緒なので作業効率大幅アップすることまちがいなし。
ということで自宅に余っていたApple Wireless Keyboardと昔PowerMac G5用に買ったBluetoothレシーバを会社に持ち込みトライ。
しかしこのBluetooth経由での認識に四苦八苦し、頓挫。
でもこんなことでは諦めません。「有線なら」と思い有線のApple Keyboard (US)を買ってきてリトライ。
結果的にうまくいったのでその方法についてご紹介します。
WindowsマシンでApple Keyboard (US)を快適に使うためには大きく2つの設定をします。
- キー配列をJISからUSに変更
Macbook ProをUSキーボードにしてからUSキーボードの魅力にとりつかれた僕は、iMacのキーボードもUSキーに換え、今回もUSキーボードを調達しました。
ただ通常のJIS配列とUS配列では「@」や「’」の位置が全然違うので、設定を変更します。
(もちろんJISキーボードを使う場合はこの設定は不要です。) - キーマッピングをWindows用からMac用に変更
こちらが本題。WindowsとMacでも「Windows」キーや「Control」キーの扱いなどが異なるので、この設定も変える必要があります。
以下にその詳細を。
- キー配列をJISからUSに変更
- レジストリエディタを起動する
※レジストリの編集はシステムに重大な影響を及ぼす可能性があります。実施される場合は、自己責任のもと慎重にやってください! - [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\i8042prt\Parameters]を右クリックし、「エクスポート」を選択してレジストリファイルをバックアップしておく
- 下記の通り値を変更する
- 「LayerDriver JPN」:kbd106.dll → kbd101.dll
- 「OverideKeyboardIdentifier」: PCAT_106KEY → PCAT_101KEY
- 「OverrideKeyBoardSubtype」:2 → 0
ちなみに、ノートPCのように「内蔵キーボードはJIS配列だけど外付けUSBキーボードはUS配列を使いたい!」ということもあると思います。この場合は、上記の一番最後「OverrideKeyBoardSubtype」は変えないでおきましょう。
- パソコンを再起動する
以上でJIS配列からUS配列への変更は終了です。
- レジストリエディタを起動する
- キーマッピングをWindows用からMac用に変更
- 以下のアプリケーション/ドライバのどれかをインストールする。
- AppleK Pro
有料ドライバですが、その完成度は有料の価値があります。これもレジストリをいじるので、ログオフ状態でも「Command+Option+Escape」を押せば「Ctrl+Alt+Delete」に!ただ、逆に言えばレジストリをいじるが故に、簡単にキー配列を戻せないのでふとWinキーボードを使ったりするとかなり面倒なことになります。 - AppleKbWin
僕が使っているのはコレ。フリーの常駐型アプリケーションなので、アプリを終了させるだけでいつものWin配列に戻すことができます。「Eject」キーを「Delete」キーに変えられなかったりFunctionキーを使えなかったり、ちょっと機能に不足はありますが個人的にはそこまで問題ではないです。 - Apple wireless keyboard helper for windows
こちらも常駐型フリーアプリ。Pythonで組んであるため自分でカスタマイズできるのが特長です。(ただしPython触れる人に限る。)その柔軟性故にAppleKbWinが抱えていた「Functionキーが使えない」等の問題も関係なし。ある意味最強かもしれません。ただし……Wirelessキーボードでないと認識してくれません。(僕のは有線なのでNG) - KbdApple
XP/Vista用なので、僕の現在のWindows7環境には基本的には対応していません。試してもいないのでアプリの良し悪しもよくわかりません……。
- AppleK Pro
- 以下のアプリケーション/ドライバのどれかをインストールする。
以上の手順で、今はかなり快適に会社のLet’s NoteでApple Keyboardを使ってます。
やっぱりApple Keyboardの外観、打鍵感は最高です。
ちなみに、マウスはLogicool M500を使っています。
マウスを選んだ条件は、「有線であること」「光学式であること」「カスタマイズ可能なボタンが付いていること」です。
一番大きいのは3つめ。
会社のパソコンで作業する中で、大体のキーボードショートカットは覚えているのでほとんどマウスに触らずに作業できるのですが、唯一覚えられないし覚えたとしてもそのショートカット押すのが結構面倒ってのがExcelのシート切り替えです。
Excelのシートのタブは小さいので押し間違えることも多いし、長い名前のシートが沢山あったりするとあっちに行ったりこっちに来たりすることが頻繁。
これはかなりのフラストレーションの元になるし、生産性を損ないます。
てことでこの「Excelのシート切り替えボタンが使えるマウス」ってところが非常に重要なポイント。
これらの条件を満たすのがLogicool M500。
価格.comなどでも高評価ですが、このマウス、ほんとにいいです。
低廉な価格ながらシンプルな機能、安定した作り。素晴らしい。
さらにマウスのボタンにアサインする機能をアプリケーションごとに変えられる、ってところも秀逸。
マウスの親指側についている「進む/戻る」ボタンは、Internet Explorer使用時には「次のページに進む」「前のページに戻る」ボタンとして、Excel使用時には「次のシートに移る」「前のシートに戻る」ボタンとして機能。うーん、最高。
しかし、1つ問題が発生。
どうやらExcel2010を使っていると、この「進む/戻る」ボタンが機能しないのです。色々設定変えてみてもダメ。
結局Logicoolのサポートに教えてもらったやり方で解決したので、その方法を解説します。
- Logicoolの設定アプリ「Setpoint」を起動して、「詳細設定」タブ→「設定」ボタンをクリック。
- 4番ボタン(「進む」ボタン)をクリックし、「キーストロークの割当」を選択、キーストロークに「Ctrl+PageUp」を入力。5番ボタン(「戻る」ボタン)も同様に「Ctrl+PageDown」を入力。
これであっさり解決です。
これでまたサクサクシートの切り替えができる~。
仕事とはいえ毎日使うマウスとキーボード。
ほんの少し自分好みにするだけで、仕事のやる気も生産性も身体への負担も全然違います。みなさんも是非ベストな組み合わせを見つけてみてはいかがでしょうか?[tmkm-amazon]B002TOJHA4[/tmkm-amazon][tmkm-amazon]B002A7Y41C[/tmkm-amazon]

コメントを残す